2023年12月
#俺ヒロ 性行為匂わせ、キス等があるやや恥ずかしき文章
2023年の2月、文章書くのにハマってたんだな…
幸せは、あなたのかたちをしてるから
ひまりが泊まりに来る日は、ひまりを先に風呂に入れて、交代で俺が入る。一緒に風呂に入るのは、恥ずかしいから、たまに。普段は風呂なんてシャワーだけで済ませて、一瞬で終わるけれど。リビングからドライヤーの音が聞こえなくなるまで、ゆっくり湯船に浸かる。
一度、俺がひまりの髪の毛を乾かしたことがあったけど、なんか、仕上がり? そういうのが……いつもとちがくて。ひまりは少しも気にしてなかったってか、髪の毛を触られて気持ち良さそうにしてたけど(……多分な?)、なんか、俺はやらないほうがいいのかもな……って思って、それからやってない。
「おかえり~」
スウェットに着替えて、リビングに戻ると、すっかり髪の毛なんかツヤツヤでサラサラになったひまりが、スマホを片手に、床にぺたんと座ってテレビを観ていた。いや、スマホのほうがメインだろうから、観ていたというより、流していたというほうが正しいか。俺が「ケツ痛くなるだろ」と椅子に座るように促すと、ひまりは立ち上がって、俺の腕を引っ張る。そのまま、「どーぞー」と、逆に俺が座らされてしまった。
「力つーよ。なんだよ。」
「ドライヤーするの。」
「あー、お願いします。」
「はーい!」
俺が1回きりにしたあとから、「じゃあうちがやる!」と、ひまりが俺の髪の毛を乾かすようになった。小さい手て頭をまさぐられる感覚はいつまでたっても慣れないが、気持ちいい。ついウトウトと舟を漕いでしまったらしく、耳元で「礼央くん」とささやかれたのも束の間、そのまま耳をはむ、と唇で噛まれてハッと姿勢を正した。
「ッ、お前さぁ……!」
「えへへ、ごめんごめん。聞こえないかなあと思いましてー。」
「……。」
俺たちは、高2の終わりころに付き合いだして、もう1年とちょっとが経過している。大学は別々だけど、同じまちに出てきて、お互い一人暮らし。お互いの地下鉄の最寄り駅に行くには、乗り換えが必要。そもそも地下鉄なんてものはなくて、家が近所で、通う学校が同じだったあの頃とは、物理的な距離が大きく開いた。
けれど、新しい生活と、地元の何十倍も栄えているこのまちは、俺たちに色々な刺激を与えてくれて、絆……ていうのか、なんつーか。仲の良さ、そういうのは、毎日積み重なっている。と、思う。学業や慣れないバイトの合間を縫って、泊まりに行ったり来たりしている。大体、週に1回。それに加えて別の日にデートをする週ももちろんある。
引っ越したばかりの頃は、全然会う暇が無かった……こともなく、逆に、新生活で、あれがいる、これがいる……どこで買う? どうしよう? っていう悩みが共有できて、解決するために一緒にまちの中心地へ出たりしていたから、会わない週っていうのは、今のところ、珍しい。
高校のころと比べて幾分も軽くなった俺の髪が乾くのはあっという間で、ひまりはドライヤーを片付けながら、ぽつりと呟いた。
「ねえ、ごめんね」
「ん、何が」
「はむはむって、したこと……。」
「怒ってねえよ、全然。ほら。」
両手を広げると、膝の上に向かい合わせになるように跨ってくる。俺が抱きしめる前に、ひまりから抱き着いてきたから、返すように、ぎゅう、と抱きしめる。髪の毛をゆっくりと撫でながら、耳に唇を近づける。「仕返し。」と囁くと、背中に回された腕に、より力が入るのを感じた。赤くなったひまりの小さい耳たぶに、触れるだけみたいなキスをする。首元に顔を埋めると、「ふふっ」と笑い声が聞こえて、頭を犬を撫でるみたいにされた。
「髪の毛、伸びてきたね。」
「ん……、そろそろ切るかな……。」
「高校生のときみたいに、伸ばさないの?」
「アレは、伸ばしてたワケじゃねえ……、だらしなかった、だけ……。」
「うちは好きだったけどなあ。」
「ふぅん……、俺もお前の……、あれ……、ツインテールみたいな……おさげ? ……好き、だったけど……今の……下ろしてるのも好き……。」
「ねえー、ずる! うちだって今の礼央くんも好きだよ。てゆうか眠い?」
「ねむ……くないッ……!」
「わっ!」
頭を撫でられるとやっぱり眠くなる。今もまた寝そうになったが、無理やり意識を引き戻し、ひまりを抱えて立ち上がった。
「歯は磨いた……な。」
「うんっ……。」
俺はひまりを抱えたまま、リビングの電気を消す。開けっ放しの襖の奥にある、寝室へ。二階だから、カーテンを開けて寝ている。朝は陽の光が、夜は微かに街灯と、月の光が入ってくる。
ひまりが風呂に入っている間、自分の布団と来客用の布団をピッタリとくっつけて、デカい敷布団みたいにしておくのが癖になっている。最初は俺のだけ敷けばいいかなって思ってたけど、起きた時にどっちかが床の上で寝てるので、一応その対策として。
来客用の布団にひまりを降ろすと、すぐに俺の布団にころころと転がるのが、暗くてもわかった。かわいい。俺も一緒に自分の布団に入ると、ひまりが「へへへ~」と笑いながら抱き着いてくる。堪らなくなって、抱きしめて、小さな唇に、チュッと軽いキスをした。
「……」
「もっとしてって顔?」
「暗いから見えないもん。」
「見えますよ。見えてんだろ? つーかそれ、認めてんじゃん。」
「……じゃあ礼央くんは、もっとチューするぞって顔、してる。」
「やっぱ見えてねーのかな。……いや、でもまあ、正解……んっ」
大学生になって、初めて俺の家に泊まりに来た時に、初めてそういうことをした。キスは高校生の時から何度かしていたけれど、それ以上のことは、する場所も、余裕もなく。初めての夜は、緊張して、恥ずかしくて、興奮して、色々な感情がまぜこぜのメチャクチャになって。今日はここまでにしようって言っても、やめないでって言われて。やっとひとつになったとき。きっと辛さで、目尻に涙を浮かべたひまりが、「うれしい」って言ってくれたから、俺は、たぶん初めて、ひまりの前で、泣いてしまった。そんなダサい俺を、ひまりは、「大丈夫? 辛い?」って、心配してきて。お前のほうだろ、それは。挿れながら泣いてる俺、ヤバイだろ。いろいろ恥ずかしくて申し訳なくて死にたくなったけど、それ以上に、好きだ、好きだ、好きだ、好きだ、好きだ……って気持ちが、溢れて止まらなくなった。
そんな記憶もまだまだ新しい。わからないことがいっぱいある。それでも、触れるようなキスから、啄むように変わって、噛みついて、深く、深くなっていく。ああ、好きだって、思いながら。
「……んぅ……ん~……んふふふっ」
「ンッ……、は……、なに……くすぐったい?」
「んん、ちがう、ごめんごめん、ふふ」
ころころと、楽しそうに笑って、俺を愛おしそうに見つめてくれるひまりが、可愛いくて、でも、なんだよって気持ちがあって、ちいさい鼻の先を指先でつつく。
「ナンデスカ。」
「笑わない?」
「はぁ? お前が先に笑ったんだろ。笑ってやるよ。」
「え! よくかんがえたら、礼央くんが笑うなら、そのほうがよくなってきた。」
「なんなんだよ……俺の表情筋の、信頼度低いな……。」
「だってさーぁ。じゃあ笑ってね? ……あのね、幸せだなって思ったら、なんか、うれしくて、笑っちゃっただけだよ。」
「……そーかよ」
そんなことを言われて、どうしていいか、わからなくて。どうしてこんなに、眩しいんだろう。ひまりの両頬を片手で掴んで、ひよこのくちばしみたいにしてやった。
「うー! なんかおこってう?」
「怒ってない。」
「じゃー、照れてぅ。」
「あーもう、ぴーちくぱーちく。」
手を離して、もう一度、人差し指で鼻先をつんつんとつつく。俺はなんか、こうやってひまりの鼻を触るのが好きだ。そして、ひまりの形を確かめるように、頬を両手で包んで、親指で優しく撫でると、ふふ、と笑った。そしてひまりも、俺と同じように、俺の頬を小さな手で包んでくれる。
「ねー教えて、見えない。暗いからね?」
「じゃあ電気つけるか。そしたらよく見える。」
「……」
「そんでそのままする。お前の顔も、体も、全部見る。」
「やぁだー!」
「ははっ……、俺もそれは恥ずかしい。」
「あ、笑ったなっ?」
「見えた?」
「見えた。かわいい礼央くんの顔。」
「かわいいって……」
「ね。男子に可愛いって思うのって不思議だよね。礼央くんにしか思わないよ?」
「ああ、そうかいそうかい。」
「なにさ!」
「……照れてる。」
「んー? ふっふっふ。」
俺の彼女が、満足げに、いたずらっぽく笑っている。さっきまで、エロいキスをしてたのに、ムードなんてどこかにいってしまって。それはそれで、心地良い。いま、ひまりとこうやって、くっついて、好きだって気持ちが伝わってくるのが、本当に本当に幸せだから。そして、俺も、伝えたい。
「あぁ、もう。クソッ……。かわいい。マジで大好き………。」
ひまりの体を引き寄せて、ぎゅっと抱きしめる。頭をゆっくり撫でながら、サラサラの髪の毛に軽くキスをする。おでこ、こめかみ、まぶた、頬、鼻、触れるだけのキスを繰り返す。ふと、唇にキスをしようとひまりの顔を見る。
「……やらしー顔。」
「……礼央くんも。」
「それはそうかも、な……。」
前言撤回。ムードなんてものは、あっさりとなくなれば、あっさりと戻ってきたりする。だから今日も、大好きなひまりにたくさん触れて、愛や幸せを確かめあって、夜がふけていくことになる。
了
2023-2-21畳む
2023年の2月、文章書くのにハマってたんだな…
幸せは、あなたのかたちをしてるから
ひまりが泊まりに来る日は、ひまりを先に風呂に入れて、交代で俺が入る。一緒に風呂に入るのは、恥ずかしいから、たまに。普段は風呂なんてシャワーだけで済ませて、一瞬で終わるけれど。リビングからドライヤーの音が聞こえなくなるまで、ゆっくり湯船に浸かる。
一度、俺がひまりの髪の毛を乾かしたことがあったけど、なんか、仕上がり? そういうのが……いつもとちがくて。ひまりは少しも気にしてなかったってか、髪の毛を触られて気持ち良さそうにしてたけど(……多分な?)、なんか、俺はやらないほうがいいのかもな……って思って、それからやってない。
「おかえり~」
スウェットに着替えて、リビングに戻ると、すっかり髪の毛なんかツヤツヤでサラサラになったひまりが、スマホを片手に、床にぺたんと座ってテレビを観ていた。いや、スマホのほうがメインだろうから、観ていたというより、流していたというほうが正しいか。俺が「ケツ痛くなるだろ」と椅子に座るように促すと、ひまりは立ち上がって、俺の腕を引っ張る。そのまま、「どーぞー」と、逆に俺が座らされてしまった。
「力つーよ。なんだよ。」
「ドライヤーするの。」
「あー、お願いします。」
「はーい!」
俺が1回きりにしたあとから、「じゃあうちがやる!」と、ひまりが俺の髪の毛を乾かすようになった。小さい手て頭をまさぐられる感覚はいつまでたっても慣れないが、気持ちいい。ついウトウトと舟を漕いでしまったらしく、耳元で「礼央くん」とささやかれたのも束の間、そのまま耳をはむ、と唇で噛まれてハッと姿勢を正した。
「ッ、お前さぁ……!」
「えへへ、ごめんごめん。聞こえないかなあと思いましてー。」
「……。」
俺たちは、高2の終わりころに付き合いだして、もう1年とちょっとが経過している。大学は別々だけど、同じまちに出てきて、お互い一人暮らし。お互いの地下鉄の最寄り駅に行くには、乗り換えが必要。そもそも地下鉄なんてものはなくて、家が近所で、通う学校が同じだったあの頃とは、物理的な距離が大きく開いた。
けれど、新しい生活と、地元の何十倍も栄えているこのまちは、俺たちに色々な刺激を与えてくれて、絆……ていうのか、なんつーか。仲の良さ、そういうのは、毎日積み重なっている。と、思う。学業や慣れないバイトの合間を縫って、泊まりに行ったり来たりしている。大体、週に1回。それに加えて別の日にデートをする週ももちろんある。
引っ越したばかりの頃は、全然会う暇が無かった……こともなく、逆に、新生活で、あれがいる、これがいる……どこで買う? どうしよう? っていう悩みが共有できて、解決するために一緒にまちの中心地へ出たりしていたから、会わない週っていうのは、今のところ、珍しい。
高校のころと比べて幾分も軽くなった俺の髪が乾くのはあっという間で、ひまりはドライヤーを片付けながら、ぽつりと呟いた。
「ねえ、ごめんね」
「ん、何が」
「はむはむって、したこと……。」
「怒ってねえよ、全然。ほら。」
両手を広げると、膝の上に向かい合わせになるように跨ってくる。俺が抱きしめる前に、ひまりから抱き着いてきたから、返すように、ぎゅう、と抱きしめる。髪の毛をゆっくりと撫でながら、耳に唇を近づける。「仕返し。」と囁くと、背中に回された腕に、より力が入るのを感じた。赤くなったひまりの小さい耳たぶに、触れるだけみたいなキスをする。首元に顔を埋めると、「ふふっ」と笑い声が聞こえて、頭を犬を撫でるみたいにされた。
「髪の毛、伸びてきたね。」
「ん……、そろそろ切るかな……。」
「高校生のときみたいに、伸ばさないの?」
「アレは、伸ばしてたワケじゃねえ……、だらしなかった、だけ……。」
「うちは好きだったけどなあ。」
「ふぅん……、俺もお前の……、あれ……、ツインテールみたいな……おさげ? ……好き、だったけど……今の……下ろしてるのも好き……。」
「ねえー、ずる! うちだって今の礼央くんも好きだよ。てゆうか眠い?」
「ねむ……くないッ……!」
「わっ!」
頭を撫でられるとやっぱり眠くなる。今もまた寝そうになったが、無理やり意識を引き戻し、ひまりを抱えて立ち上がった。
「歯は磨いた……な。」
「うんっ……。」
俺はひまりを抱えたまま、リビングの電気を消す。開けっ放しの襖の奥にある、寝室へ。二階だから、カーテンを開けて寝ている。朝は陽の光が、夜は微かに街灯と、月の光が入ってくる。
ひまりが風呂に入っている間、自分の布団と来客用の布団をピッタリとくっつけて、デカい敷布団みたいにしておくのが癖になっている。最初は俺のだけ敷けばいいかなって思ってたけど、起きた時にどっちかが床の上で寝てるので、一応その対策として。
来客用の布団にひまりを降ろすと、すぐに俺の布団にころころと転がるのが、暗くてもわかった。かわいい。俺も一緒に自分の布団に入ると、ひまりが「へへへ~」と笑いながら抱き着いてくる。堪らなくなって、抱きしめて、小さな唇に、チュッと軽いキスをした。
「……」
「もっとしてって顔?」
「暗いから見えないもん。」
「見えますよ。見えてんだろ? つーかそれ、認めてんじゃん。」
「……じゃあ礼央くんは、もっとチューするぞって顔、してる。」
「やっぱ見えてねーのかな。……いや、でもまあ、正解……んっ」
大学生になって、初めて俺の家に泊まりに来た時に、初めてそういうことをした。キスは高校生の時から何度かしていたけれど、それ以上のことは、する場所も、余裕もなく。初めての夜は、緊張して、恥ずかしくて、興奮して、色々な感情がまぜこぜのメチャクチャになって。今日はここまでにしようって言っても、やめないでって言われて。やっとひとつになったとき。きっと辛さで、目尻に涙を浮かべたひまりが、「うれしい」って言ってくれたから、俺は、たぶん初めて、ひまりの前で、泣いてしまった。そんなダサい俺を、ひまりは、「大丈夫? 辛い?」って、心配してきて。お前のほうだろ、それは。挿れながら泣いてる俺、ヤバイだろ。いろいろ恥ずかしくて申し訳なくて死にたくなったけど、それ以上に、好きだ、好きだ、好きだ、好きだ、好きだ……って気持ちが、溢れて止まらなくなった。
そんな記憶もまだまだ新しい。わからないことがいっぱいある。それでも、触れるようなキスから、啄むように変わって、噛みついて、深く、深くなっていく。ああ、好きだって、思いながら。
「……んぅ……ん~……んふふふっ」
「ンッ……、は……、なに……くすぐったい?」
「んん、ちがう、ごめんごめん、ふふ」
ころころと、楽しそうに笑って、俺を愛おしそうに見つめてくれるひまりが、可愛いくて、でも、なんだよって気持ちがあって、ちいさい鼻の先を指先でつつく。
「ナンデスカ。」
「笑わない?」
「はぁ? お前が先に笑ったんだろ。笑ってやるよ。」
「え! よくかんがえたら、礼央くんが笑うなら、そのほうがよくなってきた。」
「なんなんだよ……俺の表情筋の、信頼度低いな……。」
「だってさーぁ。じゃあ笑ってね? ……あのね、幸せだなって思ったら、なんか、うれしくて、笑っちゃっただけだよ。」
「……そーかよ」
そんなことを言われて、どうしていいか、わからなくて。どうしてこんなに、眩しいんだろう。ひまりの両頬を片手で掴んで、ひよこのくちばしみたいにしてやった。
「うー! なんかおこってう?」
「怒ってない。」
「じゃー、照れてぅ。」
「あーもう、ぴーちくぱーちく。」
手を離して、もう一度、人差し指で鼻先をつんつんとつつく。俺はなんか、こうやってひまりの鼻を触るのが好きだ。そして、ひまりの形を確かめるように、頬を両手で包んで、親指で優しく撫でると、ふふ、と笑った。そしてひまりも、俺と同じように、俺の頬を小さな手で包んでくれる。
「ねー教えて、見えない。暗いからね?」
「じゃあ電気つけるか。そしたらよく見える。」
「……」
「そんでそのままする。お前の顔も、体も、全部見る。」
「やぁだー!」
「ははっ……、俺もそれは恥ずかしい。」
「あ、笑ったなっ?」
「見えた?」
「見えた。かわいい礼央くんの顔。」
「かわいいって……」
「ね。男子に可愛いって思うのって不思議だよね。礼央くんにしか思わないよ?」
「ああ、そうかいそうかい。」
「なにさ!」
「……照れてる。」
「んー? ふっふっふ。」
俺の彼女が、満足げに、いたずらっぽく笑っている。さっきまで、エロいキスをしてたのに、ムードなんてどこかにいってしまって。それはそれで、心地良い。いま、ひまりとこうやって、くっついて、好きだって気持ちが伝わってくるのが、本当に本当に幸せだから。そして、俺も、伝えたい。
「あぁ、もう。クソッ……。かわいい。マジで大好き………。」
ひまりの体を引き寄せて、ぎゅっと抱きしめる。頭をゆっくり撫でながら、サラサラの髪の毛に軽くキスをする。おでこ、こめかみ、まぶた、頬、鼻、触れるだけのキスを繰り返す。ふと、唇にキスをしようとひまりの顔を見る。
「……やらしー顔。」
「……礼央くんも。」
「それはそうかも、な……。」
前言撤回。ムードなんてものは、あっさりとなくなれば、あっさりと戻ってきたりする。だから今日も、大好きなひまりにたくさん触れて、愛や幸せを確かめあって、夜がふけていくことになる。
了
2023-2-21畳む
#俺ヒロ バレンタイン-2年目編-
4の続き
2月14日。
高校に入学してそろそろ二年が経とうとしている。一年生のころはずっと寝たふりをしていた休み時間も、今では周りと軽い雑談をするようにまで変わっていた。
今日は朝から、心なしか教室全体を甘い香りが包んでいて、ふわふわと浮足立っているような気がする。昔だったらそれが不快で不快で堪らなくて、さっさと逃げ出していた気がするが、今年は不思議とそうでもない。
後ろの席の男子と、チョコ欲しいとか、さっきの授業クソ眠かったとか、とりとめのない話をていたら、近くの女子がこちらに振り返り、話しかけてきた。
「ね。日比生たちもチョコいる?ゆーてチロルだけどw」
「…え、マジか。やった。サンキュ…。」
「あ、あたしもー。ごめん手で取ってw全然無くならないから3個くらい食べてほしい。てか手作り大丈夫?」
差し出された大きめのタッパーには、一口サイズに切られたガトーショコラが、わりと雑に詰め込まれていた。
去年の自分からは考えられない……。クラスの女子の「義理チョコをついでにあげてもいい」リストみたいなヤツに、俺が入っているッ!!!!まあ、今一緒に話している男子の効果がデカいと思うけど。それでも嬉しい。
「いける、ありがと…。…ん、ウメェ。」
「ラッキー!マジうれしい。な、レオも俺も今日はじめてのチョコ!!だろ?」
「それはそう。」
「3倍にして返さねーと?」
「クッキーでも焼くか。」
「ほ~ぉ。レオのクッキーはこのなまらウマいガトーショコラより価値があるって~?」
「ちげーわ。量な。3倍の量。」
「え!日比生ってお菓子作れる系?フツーに楽しみなんだけどww」
いいのでしょうか。俺がこんな会話を楽しんでしまって……。ごめんなさいクソ楽しいです。世界を呪っていたあの頃の俺が、今の俺を見たら、絶対殺しに来るでしょうね。
そんなこんなで俺は「想像上のバレンタイン」みたいな一日を、それなりに過ごしたのである。
―――しかし、だ!
帰宅して、自室の床に大の字になって呆然とする。休み時間にあまりスマホに触らなかったから、おそらく全回復したソシャゲの体力も、消費する気になれないまま。
(ひまりに貰えるとおもったのに……。)
【俺にバレンタインチョコをくれる可能性がある家族以外の人間ランキング 1位】であろう人(ランクインしてるの、一人しかいないけど)から、貰えなかった。
というか、今朝は同じバスで、同じ教室に登校したが、バレンタインのバの字も会話には出なかったし、なんなら、教室についてから、一度も会話をしていなかった。
(……今日はずっと誰かと話してたから、気づかなかった。ひまりと話さない日も、あるんだな、俺。)
帰りも会うことはなかった。俺は掃除当番だったし、ひまりはさっさと部活に行ったのだろう。
ちょっと前の俺だったら。
勝手に期待して、貰えなかったことに拗ねて、「騙された」とか「詐欺だ」とか「好きじゃないのかよ俺のこと」とか、なんかそういう……逆ギレをしていた。
思春期のせいといえばそうなのかもしれない。インターネットに毒されているのもそうだ。とにかく何をされたわけでもないのに、俺はずっと誰かにバカにされているような気がしていて。全部自分が周りをバカにしていただけだったのに。それに気づけたのは最近で、教えてくれたのはひまりで。今日のバレンタインが憎くなかったのも、クラスメイトと雑談ができたのも、全部全部、ひまりが俺の目をまっすぐ見つめて、話してくれたから。もっと、人と関わってもいいのかもって、思わせてくれたから。
(欲しいって、言えばよかったんじゃね。)
だから、だから、もっと素直になっても、絶対バカになんかしてこないって、もうわかっている。俺はひまりのことが好きなんだ。ひまりが俺のことを好きじゃなくたって別にいい。いや、よくはないけど。……まあとにかく、俺が、今日の、バレンタインっていう日に、ひまりからチョコレートをもらいたかったって、伝えても、きっと大丈夫……、大丈夫。だと思いたい。
昨夜ひまりから来た「おやすみ」のスタンプで止まっているライン。入力欄に何度も文字を打っては消して、打っては消してを繰り返す。そうしていると、画面が切り替わって突然音楽が流れる。ひまりから、電話がかかってきたことを認識するのに、若干のラグがあった。びっくりした。嘘。なんだろ。え?マジか。ああ、えっと。あぁああ!?
「ッ、…ンッ、もしもし?」
「あ、礼央くんっ、あの……」
「何?どした」
「今、部活終わって、バス待ってて…、それで。」
「うん」
「えと、……バス停に、迎えに、きてほしい、…です。一応あと30分くらいで着く、から……。あー、えっと、ごめん、いきなりだよね、えーとね……。」
「そんなことかよ。わかった。」
「え」
「待ってるから。寝過ごすなよ?」
「う、うん!あっバス来た。じゃあねっ」
ドクンと心臓が脈を打つのをハッキリと感じる。通話の切れたスマホを、しばらく耳から離せない。
"そんなことかよ"なんてカッコつけたけど、実際は、何で?なんで?なんで!?って聞きたかった。でも理由なんて聞くのはどう考えても野暮だろ!
"絶対騙されてる"、"何かのドッキリ"、"行ったら陰で笑われる"……前の俺ならこういう思考回路になっていて。でもよく考えたら俺って、別に人生で一度も、そんな目にあってないのにな。俺は自ら不幸になろうと、そうやって生きて……自分がカワイソウであることで、自分を守っていたような。
コンビニに行ってくるとかなんとか言って、家を出る。すっかり体温が上がっているような感覚があって、自分が手袋を忘れたことに気づいたのは、停留所についてからだった。コートのポケットに手を突っ込んで、バスが来るのを待っていると、ほどなくして来た。そして降りてくるのは見慣れた顔が一人だけ。
「ッス……、おつかれ」
「礼央くんっ!」
「っ、どーした、慌てて。転ぶぞ」
ポケットから手を出して、ひまりの方に腕を伸ばす。転んでも支えられるように……、そのつもりだったが、ひまりは俺の両手を掴んで、ぶんぶんと振る。
「ほんとに来てくれた、へへ」
俺は、俺以外の人間が、キラキラしていてウザかった。部活をやっていたころはあまりそんなことは思ってなかったけど、高校に入ったら悪化した。みんなお互いを信用してて、他人からどう思われようとも気にしてないんだろうとか、なんか…まあ、そういう風に思っていた。でも、今思うのは…、むしろ、周りのことを考えるから、人間関係はうまくいくだろうし、俺なんかより、よっぽど、人の目を気にしているからこそ、キラキラしている。自分が言ったことに、相手がどう思うのか。そういうことを考えられるのが…。全員がそうだとか、そういう話じゃないけど。そういう深い話では、全然ないんだけれど。俺は、ひまりがキラキラして見える。ひまりも、俺が来なかったらどうしようって、不安に思ってくれたのか。来なかったら、嫌だなって。
「来るだろ、そりゃ。当たり前だろ。」
「そっか、…うん。ありがとう。」
「あ、当たり前って、あれだぞ。その。」
「う、うん!!わ、わかってるよ!そんなの?呼ばれたんだから…」
「わかってない、ちがくて……、お前だから」
「え……」
「ひまりだから来たんだ」
しん……と周りが静まったような気がした。
ひまりはその真ん丸い目をもっと丸くして、俺の目を見つめている。
彼女が何かを言う前に、俺が耐えられなくなって、「えーと。」と声を上げる。
「……、公園でも行く、か?」
「あっ、うん、そうだね……。」
手を離して、「お前、毎日荷物多すぎだろ」と、手提げカバンを奪って、隣に並んで歩く。
近所にある公園は、まったく除雪がされてなくて、中まで入ることができなかったから、入口あたりでたむろする形になった。
「で、何。」
「えっと……、その、かばんの中、見てっ!」
「え……、あ。」
リュックに入りきらなかった参考書に紛れて、明らかに、プレゼントしますって感じの箱が入っていた。
そっとそれを取り出してみると、表面には「礼央くんへ」と宛名が書かれたカードが貼られていた。
「俺のだ。」
「そうだよ!」
「やった~。」
「やったー!?あはっ!」
「なんだよ。」
「だって、普段、そんなこと言わないから。」
「そーだっけ。」
「そーだよ!」
「俺に詳しいですね。」
「……まあね!」
「開けて良い?開ける。…あ、マフィンだ。うまそ。」
「今年は、作りました…。」
さっきまで緊張で引きつっていたひまりの表情が、だんだんといつもどおりになっていく。
赤くなった頬は、寒さか、それともそれ以外か。もらったプレゼントは一度手提げカバンにしまわせてもらって、そのまま自分の腕にひっかける。頬の温度を確かめるように、俺はひまりの頬を両手で包んだ。
「ちゅめた!」
「あ、悪い……」
「いいよ、そのままで。あっためてあげる」
ひまりはその両手を、俺の手に重ねる。去年と同じ手袋で、変わらず指先を余らせている、小さくて、……愛おしい手だった。
「ありがとう。」
「どういたしまして」
「手じゃなくて。手もだけど。……バレンタイン、だよな。」
「……うん。」
「ひまりにもらえないから、よこせって、ダダこねようかと思ってた。」
「そ、そうなの!?」
「そうなの。」
「うち、ほんとは……、学校であげようと思ったんだけどね」
「うん」
「礼央くん、休み時間、ずっとチョコもらってたし……」
「義理の義理の義理の義理くらいのやつな?」
「それでも……」
「ふーん。それで、拗ねたんだ。」
「ちが……、ちがくないね。うん。拗ねた……。」
「……そ、すか……。」
揶揄うつもりで言ったことが、素直に肯定される、カウンター攻撃。ひまりと一緒にいれば、珍しいことではなかったが、それでも毎回、まともにくらってしまう。今までも何度もこういう……恋愛イベントみたいなことがいっぱいあって。きっとひまりも俺も、そのフラグが回収しきれないことに、心地よさを感じているんだと思う。でも、俺はもう限界だった。ひまりと俺が関わるようになったきっかけも、去年のバレンタインだった。そんなあまりにも出来すぎた舞台も手伝って、もう、今日、今、この瞬間、もうダメだって思った。俺は今、目の前にいる大好きな女の子を、抱きしめて、キスをして、大好きだっていっぱい伝えたい。
「あー、好きだ。」
「え、あ…」
「真面目に。彼氏にしてくれ。」
「ッ!!!うちも、礼央くんのこと、好き!!大好き!!真面目なのっ!!彼女にして!!」
「どーしたんだよ、急に、……ははっ……はーあ。力抜ける……。」
ひまりの頬から手を離して、そのまま片手をつなぐ。
「今日はもー、帰るか。寒い。」
「う、うん!」
「……あー、その、さ。」
「んっ?」
「不束者ですが…、よろしくお願いします」
「……こちらこそ、お願いします。」
俺は愛しさを噛みしめるように、繋いだ手に力を込めた。
了
2023-2-16畳む
4の続き
2月14日。
高校に入学してそろそろ二年が経とうとしている。一年生のころはずっと寝たふりをしていた休み時間も、今では周りと軽い雑談をするようにまで変わっていた。
今日は朝から、心なしか教室全体を甘い香りが包んでいて、ふわふわと浮足立っているような気がする。昔だったらそれが不快で不快で堪らなくて、さっさと逃げ出していた気がするが、今年は不思議とそうでもない。
後ろの席の男子と、チョコ欲しいとか、さっきの授業クソ眠かったとか、とりとめのない話をていたら、近くの女子がこちらに振り返り、話しかけてきた。
「ね。日比生たちもチョコいる?ゆーてチロルだけどw」
「…え、マジか。やった。サンキュ…。」
「あ、あたしもー。ごめん手で取ってw全然無くならないから3個くらい食べてほしい。てか手作り大丈夫?」
差し出された大きめのタッパーには、一口サイズに切られたガトーショコラが、わりと雑に詰め込まれていた。
去年の自分からは考えられない……。クラスの女子の「義理チョコをついでにあげてもいい」リストみたいなヤツに、俺が入っているッ!!!!まあ、今一緒に話している男子の効果がデカいと思うけど。それでも嬉しい。
「いける、ありがと…。…ん、ウメェ。」
「ラッキー!マジうれしい。な、レオも俺も今日はじめてのチョコ!!だろ?」
「それはそう。」
「3倍にして返さねーと?」
「クッキーでも焼くか。」
「ほ~ぉ。レオのクッキーはこのなまらウマいガトーショコラより価値があるって~?」
「ちげーわ。量な。3倍の量。」
「え!日比生ってお菓子作れる系?フツーに楽しみなんだけどww」
いいのでしょうか。俺がこんな会話を楽しんでしまって……。ごめんなさいクソ楽しいです。世界を呪っていたあの頃の俺が、今の俺を見たら、絶対殺しに来るでしょうね。
そんなこんなで俺は「想像上のバレンタイン」みたいな一日を、それなりに過ごしたのである。
―――しかし、だ!
帰宅して、自室の床に大の字になって呆然とする。休み時間にあまりスマホに触らなかったから、おそらく全回復したソシャゲの体力も、消費する気になれないまま。
(ひまりに貰えるとおもったのに……。)
【俺にバレンタインチョコをくれる可能性がある家族以外の人間ランキング 1位】であろう人(ランクインしてるの、一人しかいないけど)から、貰えなかった。
というか、今朝は同じバスで、同じ教室に登校したが、バレンタインのバの字も会話には出なかったし、なんなら、教室についてから、一度も会話をしていなかった。
(……今日はずっと誰かと話してたから、気づかなかった。ひまりと話さない日も、あるんだな、俺。)
帰りも会うことはなかった。俺は掃除当番だったし、ひまりはさっさと部活に行ったのだろう。
ちょっと前の俺だったら。
勝手に期待して、貰えなかったことに拗ねて、「騙された」とか「詐欺だ」とか「好きじゃないのかよ俺のこと」とか、なんかそういう……逆ギレをしていた。
思春期のせいといえばそうなのかもしれない。インターネットに毒されているのもそうだ。とにかく何をされたわけでもないのに、俺はずっと誰かにバカにされているような気がしていて。全部自分が周りをバカにしていただけだったのに。それに気づけたのは最近で、教えてくれたのはひまりで。今日のバレンタインが憎くなかったのも、クラスメイトと雑談ができたのも、全部全部、ひまりが俺の目をまっすぐ見つめて、話してくれたから。もっと、人と関わってもいいのかもって、思わせてくれたから。
(欲しいって、言えばよかったんじゃね。)
だから、だから、もっと素直になっても、絶対バカになんかしてこないって、もうわかっている。俺はひまりのことが好きなんだ。ひまりが俺のことを好きじゃなくたって別にいい。いや、よくはないけど。……まあとにかく、俺が、今日の、バレンタインっていう日に、ひまりからチョコレートをもらいたかったって、伝えても、きっと大丈夫……、大丈夫。だと思いたい。
昨夜ひまりから来た「おやすみ」のスタンプで止まっているライン。入力欄に何度も文字を打っては消して、打っては消してを繰り返す。そうしていると、画面が切り替わって突然音楽が流れる。ひまりから、電話がかかってきたことを認識するのに、若干のラグがあった。びっくりした。嘘。なんだろ。え?マジか。ああ、えっと。あぁああ!?
「ッ、…ンッ、もしもし?」
「あ、礼央くんっ、あの……」
「何?どした」
「今、部活終わって、バス待ってて…、それで。」
「うん」
「えと、……バス停に、迎えに、きてほしい、…です。一応あと30分くらいで着く、から……。あー、えっと、ごめん、いきなりだよね、えーとね……。」
「そんなことかよ。わかった。」
「え」
「待ってるから。寝過ごすなよ?」
「う、うん!あっバス来た。じゃあねっ」
ドクンと心臓が脈を打つのをハッキリと感じる。通話の切れたスマホを、しばらく耳から離せない。
"そんなことかよ"なんてカッコつけたけど、実際は、何で?なんで?なんで!?って聞きたかった。でも理由なんて聞くのはどう考えても野暮だろ!
"絶対騙されてる"、"何かのドッキリ"、"行ったら陰で笑われる"……前の俺ならこういう思考回路になっていて。でもよく考えたら俺って、別に人生で一度も、そんな目にあってないのにな。俺は自ら不幸になろうと、そうやって生きて……自分がカワイソウであることで、自分を守っていたような。
コンビニに行ってくるとかなんとか言って、家を出る。すっかり体温が上がっているような感覚があって、自分が手袋を忘れたことに気づいたのは、停留所についてからだった。コートのポケットに手を突っ込んで、バスが来るのを待っていると、ほどなくして来た。そして降りてくるのは見慣れた顔が一人だけ。
「ッス……、おつかれ」
「礼央くんっ!」
「っ、どーした、慌てて。転ぶぞ」
ポケットから手を出して、ひまりの方に腕を伸ばす。転んでも支えられるように……、そのつもりだったが、ひまりは俺の両手を掴んで、ぶんぶんと振る。
「ほんとに来てくれた、へへ」
俺は、俺以外の人間が、キラキラしていてウザかった。部活をやっていたころはあまりそんなことは思ってなかったけど、高校に入ったら悪化した。みんなお互いを信用してて、他人からどう思われようとも気にしてないんだろうとか、なんか…まあ、そういう風に思っていた。でも、今思うのは…、むしろ、周りのことを考えるから、人間関係はうまくいくだろうし、俺なんかより、よっぽど、人の目を気にしているからこそ、キラキラしている。自分が言ったことに、相手がどう思うのか。そういうことを考えられるのが…。全員がそうだとか、そういう話じゃないけど。そういう深い話では、全然ないんだけれど。俺は、ひまりがキラキラして見える。ひまりも、俺が来なかったらどうしようって、不安に思ってくれたのか。来なかったら、嫌だなって。
「来るだろ、そりゃ。当たり前だろ。」
「そっか、…うん。ありがとう。」
「あ、当たり前って、あれだぞ。その。」
「う、うん!!わ、わかってるよ!そんなの?呼ばれたんだから…」
「わかってない、ちがくて……、お前だから」
「え……」
「ひまりだから来たんだ」
しん……と周りが静まったような気がした。
ひまりはその真ん丸い目をもっと丸くして、俺の目を見つめている。
彼女が何かを言う前に、俺が耐えられなくなって、「えーと。」と声を上げる。
「……、公園でも行く、か?」
「あっ、うん、そうだね……。」
手を離して、「お前、毎日荷物多すぎだろ」と、手提げカバンを奪って、隣に並んで歩く。
近所にある公園は、まったく除雪がされてなくて、中まで入ることができなかったから、入口あたりでたむろする形になった。
「で、何。」
「えっと……、その、かばんの中、見てっ!」
「え……、あ。」
リュックに入りきらなかった参考書に紛れて、明らかに、プレゼントしますって感じの箱が入っていた。
そっとそれを取り出してみると、表面には「礼央くんへ」と宛名が書かれたカードが貼られていた。
「俺のだ。」
「そうだよ!」
「やった~。」
「やったー!?あはっ!」
「なんだよ。」
「だって、普段、そんなこと言わないから。」
「そーだっけ。」
「そーだよ!」
「俺に詳しいですね。」
「……まあね!」
「開けて良い?開ける。…あ、マフィンだ。うまそ。」
「今年は、作りました…。」
さっきまで緊張で引きつっていたひまりの表情が、だんだんといつもどおりになっていく。
赤くなった頬は、寒さか、それともそれ以外か。もらったプレゼントは一度手提げカバンにしまわせてもらって、そのまま自分の腕にひっかける。頬の温度を確かめるように、俺はひまりの頬を両手で包んだ。
「ちゅめた!」
「あ、悪い……」
「いいよ、そのままで。あっためてあげる」
ひまりはその両手を、俺の手に重ねる。去年と同じ手袋で、変わらず指先を余らせている、小さくて、……愛おしい手だった。
「ありがとう。」
「どういたしまして」
「手じゃなくて。手もだけど。……バレンタイン、だよな。」
「……うん。」
「ひまりにもらえないから、よこせって、ダダこねようかと思ってた。」
「そ、そうなの!?」
「そうなの。」
「うち、ほんとは……、学校であげようと思ったんだけどね」
「うん」
「礼央くん、休み時間、ずっとチョコもらってたし……」
「義理の義理の義理の義理くらいのやつな?」
「それでも……」
「ふーん。それで、拗ねたんだ。」
「ちが……、ちがくないね。うん。拗ねた……。」
「……そ、すか……。」
揶揄うつもりで言ったことが、素直に肯定される、カウンター攻撃。ひまりと一緒にいれば、珍しいことではなかったが、それでも毎回、まともにくらってしまう。今までも何度もこういう……恋愛イベントみたいなことがいっぱいあって。きっとひまりも俺も、そのフラグが回収しきれないことに、心地よさを感じているんだと思う。でも、俺はもう限界だった。ひまりと俺が関わるようになったきっかけも、去年のバレンタインだった。そんなあまりにも出来すぎた舞台も手伝って、もう、今日、今、この瞬間、もうダメだって思った。俺は今、目の前にいる大好きな女の子を、抱きしめて、キスをして、大好きだっていっぱい伝えたい。
「あー、好きだ。」
「え、あ…」
「真面目に。彼氏にしてくれ。」
「ッ!!!うちも、礼央くんのこと、好き!!大好き!!真面目なのっ!!彼女にして!!」
「どーしたんだよ、急に、……ははっ……はーあ。力抜ける……。」
ひまりの頬から手を離して、そのまま片手をつなぐ。
「今日はもー、帰るか。寒い。」
「う、うん!」
「……あー、その、さ。」
「んっ?」
「不束者ですが…、よろしくお願いします」
「……こちらこそ、お願いします。」
俺は愛しさを噛みしめるように、繋いだ手に力を込めた。
了
2023-2-16畳む



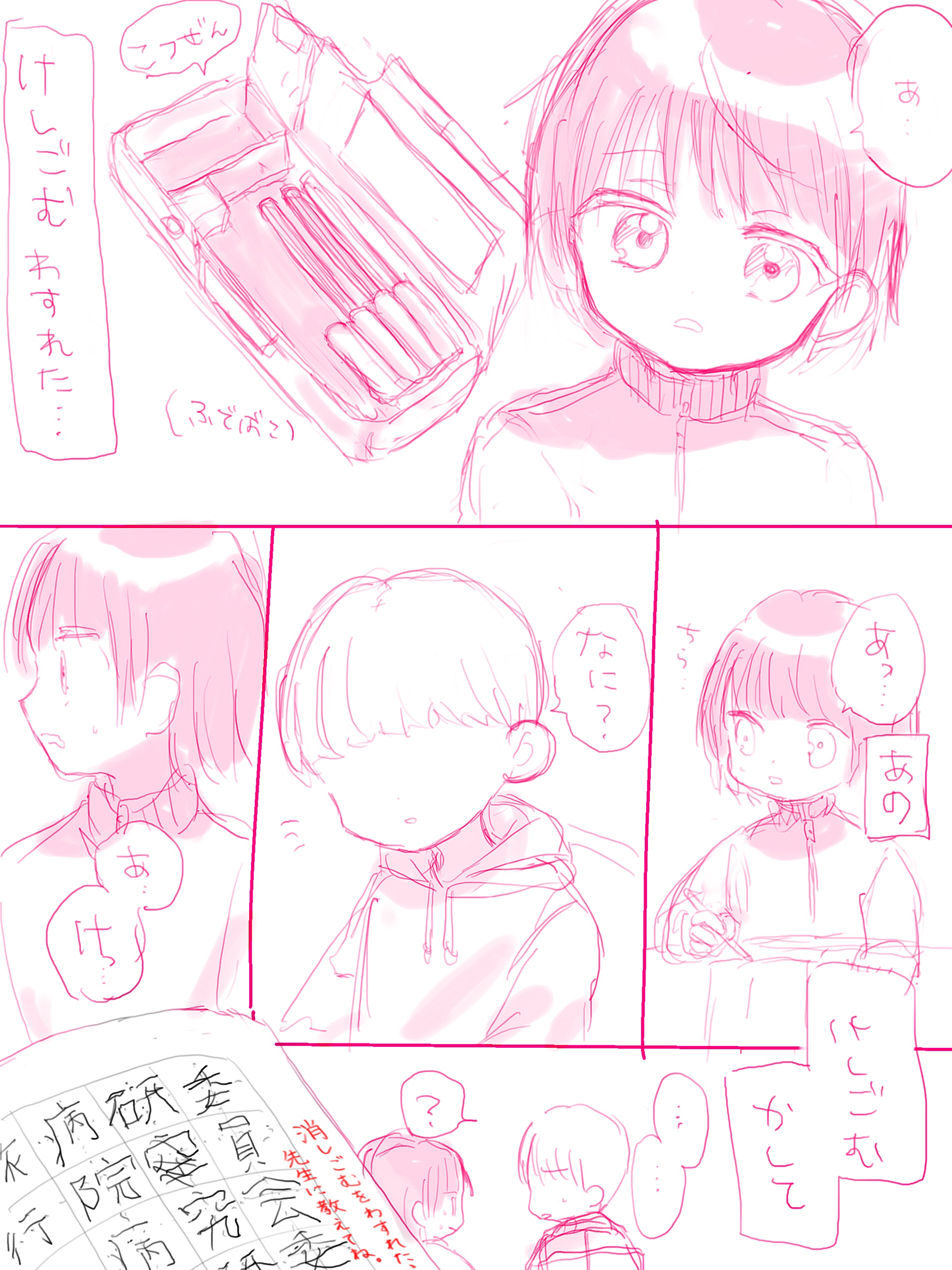

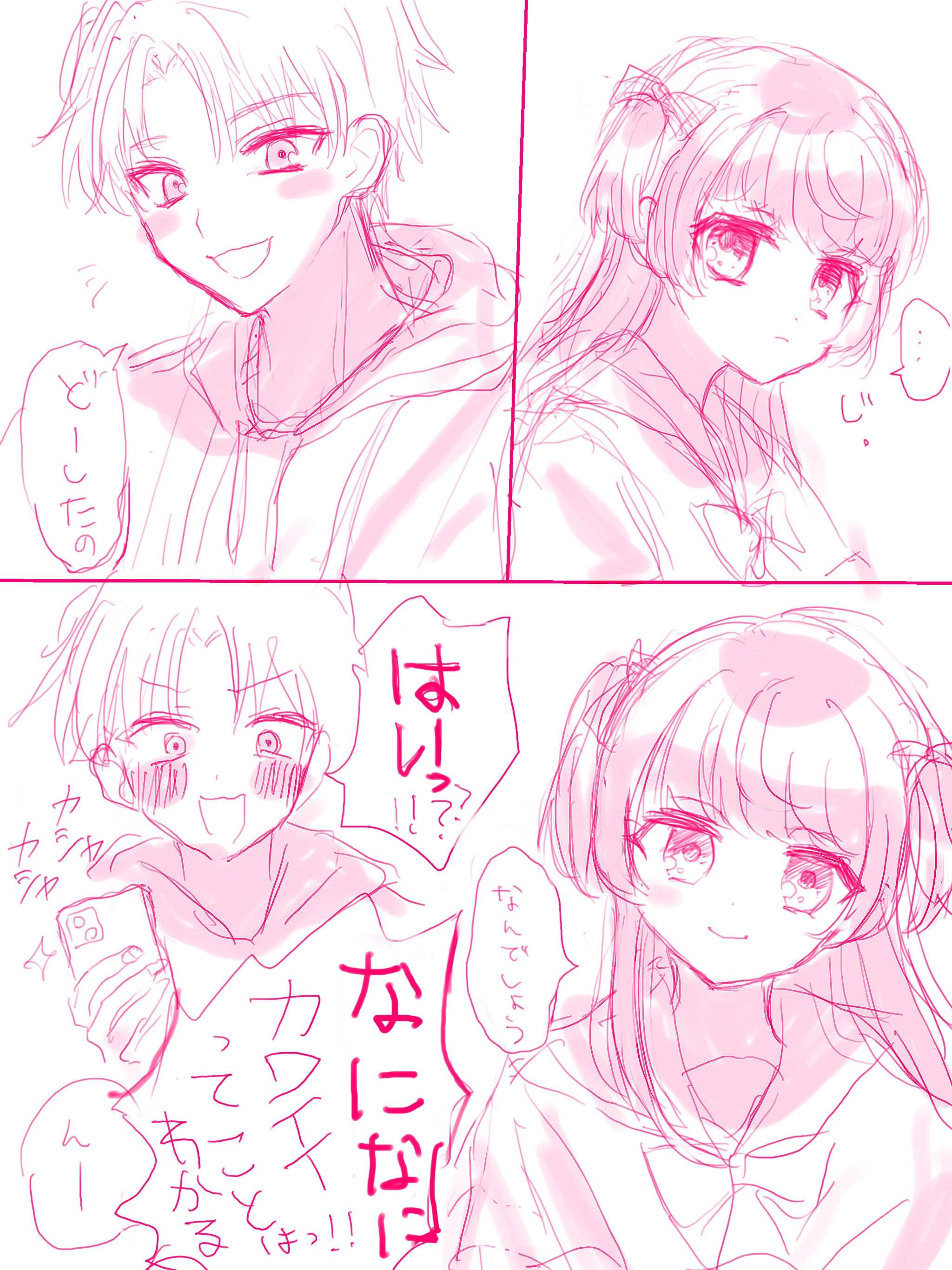
あまりにも雑汚すぎ注意
出会いみたいな
その後
おじさん好きな設定は死んだ